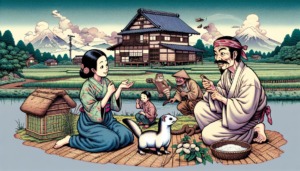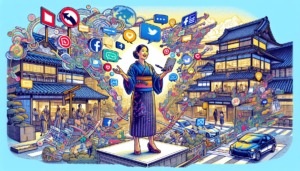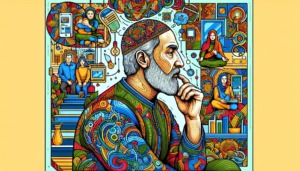{“text”:”OKファームのOKです。この記事は、音声配信でお話したものをブログ記事にしたものです。/n(この記事は音声でもお聴き頂けます。リンクはこちらからhttps://stand.fm/episodes/68970489d5d2a181b82b85f4)
はじめに
今回は法事の年の計算の仕方についてお話しします。特に、亡くなってからの初七日や四十九日、また1周忌、3回忌についての名称やその意味を知っていると、法事の準備や思い出に対する気持ちも少し楽になるかもしれませんね。今回の内容を通じて、法事が単なる儀式ではなく、故人を思い出し、心の成長を促す大切な時間であることも感じ取ってもらえたら嬉しいです。
### 法事の周期とは?
法事には、亡くなった方を偲ぶためのさまざまな儀式がありますが、その周期がどのように計算されるのか、ご存知でしょうか?
最初は「初七日」で、これは亡くなってから7日目に行われるものです。その後、二七日、三七日と続き、49日で一区切りを迎えます。ここでの法事は、故人を偲ぶだけでなく、家族や親族が集まる大事な時間です。私自身、親戚の法事に参加することで改めてその重要性を感じることができました。
### 1周忌とその先
次に、法事において特に重要な「1周忌」についてお話しします。これは亡くなってから1年後に行われる唯一の法事で、とても意味があります。私も明日、祖父の1周忌を迎えるため、準備に忙しい毎日です。この1周忌を経て、以降の法事は、亡くなった年を引き算しながら計算していきます。
たとえば、3回忌は亡くなった年を1年目として数え、2年後に行われます。これ以降は7回忌、13回忌と続きますが、法要の回数が増えるにつれて、どうしても数え間違えがちになるので注意が必要です。
### 法事の意味と価値
法事は、ただの儀式以上の意味を持っています。私が感じるのは、法事を通じて故人との距離感が変化し、思い出して心が温まる瞬間があるということです。特に、法事の際に故人を思い出すことで、過去の出来事や思い出も振り返ることができ、自分自身の年齢も相まって、親や祖父母が当時どういう気持ちだったのかと考えたくなります。
たとえば、70歳で亡くなった父親の法事であれば、13回忌を迎えた時、自分もその年に近づき、彼の気持ちを理解するチャンスが訪れます。このように、法事を通じて故人とのつながりを再確認するのは、私にとってとても大切なことです。
### 仏教的な見解
さらに、法事に関連する仏教の見解についても少し触れたいと思います。昨日、法事について調べていると、「円摩大王」や「冤摩町」などの言葉について考える機会がありました。故人が亡くなった後、どうなるのかという仏教的な考え方はとても興味深いものがあります。今後、その内容についてもお話ししていくつもりです。
私の祖父は昨年亡くなりましたが、彼が今どこにいるのか、何をしているのかを考えることで、さまざまな気づきがありました。
ここまでお話ししたように、法事は亡くなった方を偲び、思い出すための大切な時間です。これからも法事を通じて、自分自身の成長を実感しながら、故人への感謝の気持ちを忘れずに過ごしていきたいと思います。
ここまでのお相手はOKファームのOKでした。また遊びにきんさい。ほいじゃあまたのー!”}