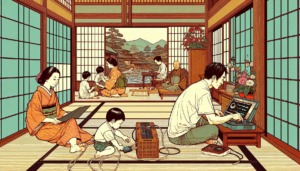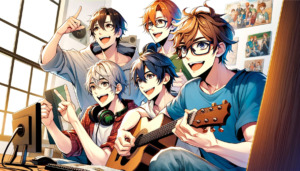{“text”:”OKファームのOKです。この記事は、音声配信でお話したものをブログ記事にしたものです。
(この記事は音声でもお聴き頂けます。リンクはこちらからhttps://stand.fm/episodes/686376306a5289da255c0d9d)
はじめに、AI技術の進化によって私たちの生活はますます便利になっていますが、一方でその便利さを過信することには注意が必要です。
実際に私自身の経験を通じて、AIの便利さとその背後に潜むリスクについてお話ししたいと思います。特に「検算」という考え方の大切さについて、詳しく掘り下げていきます。
## AIの設定ミスが引き起こした大間違い
まず最初にお話ししたいのは、私が最近経験した計算ミスについてです。
実は、80歳までの残りの寿命を計算するアプリで設定を間違えてしまい、4174週しか残っていないと表示されました。
しかし、実際には4874週も残っていることが後で分かりました。この設定ミスが、大きな誤りを引き起こす可能性があることを痛感させられました。
便利なツールであっても、**基本的な使い方や初期設定をしっかり確認しないと、信じられないような誤りが生じてしまうのです**。
## AIの進化と使うリスク
最近のAIは、ここ数年で本当に進化しています。
以前はチャットGPTのようなツールも、質問に対して限られた字数の回答しかできませんでしたが、今では数万字の文章も生成可能になっています。
それに伴い、便利さは増す一方ですが、**正確性を過信しすぎると危険な結果を招くこともあります**。
私の体験談ですが、過去の売上データをAIに分析させた時、1回目と2回目でまったく異なる結果が出てきたことがありました。
分析内容が大きく変わってしまうと、どちらが正しいのか分からず、そのまま信じ込むのは危険です。
## 検算の重要性
そんなわけで、AIが提供するデータの正確性を鵜呑みにしないためには、自分の目での確認が必要です。
例えば、AIが導き出した結果の中から数か所、まずは行ごとに確認してみることをお勧めします。
特に100行以上のデータがある場合、**最初の行、真ん中の行、最後の行など3か所をチェックするだけでも、ミスに気づきやすくなります**。
このように、検算を行うことで、意図しない計算ミスや誤情報に気づくことができるのです。
## 地域情報提供の危険
また、AIが提供する地域に関する情報でも誤りがある場合があります。
広島銀行のATM情報を調べた際にも、誤った情報が表示され、正しい情報を得るためには実行錯誤が必要でした。
知らない土地の情報をAIに頼ることは便利ですが、地域の知識がないと、おかしな結果を得るリスクもあります。
こうした情報提供の際には、自分の目で確認することが重要です。
## 最後に
今回は、AIの便利さが魅力である一方で、その過信によるリスクや検算の重要性についてお話ししました。
AIを使うときは、必ず自身での確認や検算を心掛けることが大切です。
自分の目で確かめることで、より安全にAIを活用することができると思います。
ここまでのお相手はOKファームのOKでした。また遊びにきんさい。ほいじゃあまたのー!”}